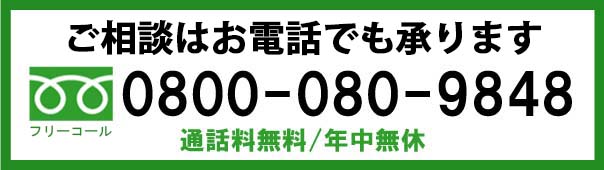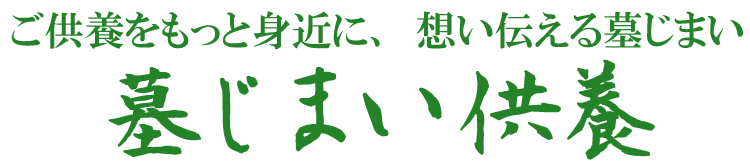最近よく聞く墓じまいの話題。
しかし、実際にやることになっても、いったい何から手を付けて良いのかわからない。
そんな状態でスタートしても失敗してしまうのではないか?と漠善と思われる方も多いのではないでしょうか?
今回は墓じまいをイメージ通りにできなかった過去の事例をいくつか並べてみます。
これから墓じまいを検討なされる方や今まさに墓じまい計画進行中の方にとっても身になる内容と思います。
皆様のご参考としていただけるとありがたいです。
事例1:管理者に届け出をしないで遺骨を勝手に埋葬していた!?
これは過去に数件経験したことがある事例ですが、
墓じまい工事に取り掛かるために、お墓の納骨棺(カロート)からご先祖の骨壺を骨上げする際に、埋葬されているはずのご遺骨よりも数が多く骨壺が見つかることがございます。
すべての骨壺などにお名前が記載されていると良いのですが、実際にはその文字が消えていたり判別できなかったりということもあり、誰のお骨なのか判別できないことも多々ございますが、とにかく数が合わない。
明治時代から続くお墓など、かなり古くから続くお墓なら管理者も当時の記録は不詳というケースもございますが、建墓後30年程度のお墓です。
すぐに墓地の管理者様とお客様に連絡を入れますが、原因は不明。
ここでよくあるのが、どうもお子様用とみられる小さな骨壺が多く入っているケースです。
そこでお客様へ「過去にペットのご遺骨を一緒に入れた記憶はございませんか?」と聞きますと「そうだ。忘れていた!○○ちゃんだ!」と当時家族の一員として飼っていたペットの記憶がよみがえり、、、
主にペットのお骨が多いのですが、当時飼っていたかわいいペットのお骨を先祖の納骨棺に一緒に埋葬しているケースが混乱を招きます。
もちろん墓地の管理者には報告していなければならないのですが、長年経つとお互いに忘れていたり、管理者も当時と現在で代わっていたり、ペットのお骨を入れることへの許可をしたのかしていないのかを確認が取れません。
因みにそこで見つかったペットのお骨は、お客様が引き取るか或いは新しい埋葬施設でペット埋葬が認められていればその施設に埋葬なされるケースが多いです。
結果、大きな問題にはならず一同安堵して工事に取り掛かりますが、思わぬ混乱で工事日が伸びてしまうこともございます。
事例 2:改葬許可を申請していない!?
このケースも過去にあった事例で、お客様から直接墓じまいの依頼を受け、既に許可を受けているかと質問したところ「許可は得ている」とのこと。
そこで、いつも通り現地墓所を確認後、お見積りから契約に至り、お客様から指定された日に工事準備のためにお寺様に伺うと「墓じまいの相談は受けたが、改葬許可申請書も見ていないし、いつ行うとも聞いていないですよ」とのこと。
すぐにお客様にお電話すると、お客様としては墓地の管理者であるご住職に意思を伝えたので工事を進めてよいと思われていたとのこと。
すぐに工事は一旦中止し、お客様とご住職とで後日打ち合わせをなされ、その後はトラブルもなく墓じまいを進めることになりました。
このケースでは私共にも落ち度があり、まず最初の現地確認の際に墓地の管理者(ご住職)がご不在であったため、お寺のご家族にお客様の墓所確認の旨を伝えるだけで墓所を確認し、その後直接お客様とだけ打ち合わせを進めて工事初日に至りましたが、管理者であるご住職に直接お電話等で改葬許可申請の書面に記載捺印なされたかの確認を取るところまで行っていれば、またはお客様へ改葬許可証を手元にあるかを確認しておけば、防げた失敗であったと反省したものです。
以降、このケースでのトラブルは回避できておりますが、”墓じまい”の名前だけが先行しているのか、埋葬済みのお墓では役場への改葬許可申請が必要であることをご存じないお客様は多いようです。
同じような事例は、割と田舎の公営墓地などで多い印象がございますが、おそらく、お客様と墓所の管理者様とで接点がない(管理事務所に管理者が在中していない)なども原因の一つかと感じました。
参考:墓じまいの改葬手順
事例3:ご自分だけで決断なされた!?(誰にも相談しなかった)
私共が墓じまい工事を行っていると、見ず知らずの男性からいきなり「何やってるんだ!」と怒鳴られました。話を聞く墓じまいの依頼者の親戚にあたる方だと。
依頼されての仕事であることを説明しますが、納得はされません。
しかし、契約をいただいているのでそのまま実行をしなくてはなりませんが、念のためお客様に電話報告。
結果、お客様からは親戚の方には後日話せばいいので、とにかくそのまま工事を進めるようにとのお答えでした。
この日は、私共が解体工事を行っている際にたまたまお近くに住むご親戚の方が目にして声をかけられましたが、おそらく私共が工事完了後、私たちは知り得ないところでお客様が親戚などから意見されることは多いのかもしれません。
かなり昔の話ではあなりますが、この時、私共もお客様に「親戚やお身内の方へもお知らせし致しましたか?」と一言お伝えするべきであったなと感じました。
ということで、墓じまいの改葬手順をご覧いただけると幸いです。
これを機に、墓じまいを計画する際は、あらかじめご親戚などにもお考えを伝えておいた方がよろしいだろうと思い、必ずお身内の方へもお知らせなされるようにお伝えしております。
参考記事:墓じまいを安くする方法
事例4:墓じまいをしたが改葬先で骨壷が入らなかった
改葬先の供養施設で、改葬する仏様の骨壷を埋葬しようとしたが、改葬先の納骨棺の口元が小さく、既存の骨壷が入らなかったというケースも度々起こります。
これはご存じない方も多いかと思いいますが、地域などによって使われる骨壷の大きさや方法が異なるためです。
一般的に西日本の骨壷は小さく、東日本は大きいと言われますが、実際にはそこまで単純なものではなく、地域や習慣によって異なるのが現状です。
もし、骨壷サイズの違いで埋葬できなかった場合は、後日小さな骨壷に移されてから埋葬することが一般的です。
スムーズに進めるためにも、墓じまい業者様に依頼して、予め骨壷の大きさを計測しておくことをお勧め致します。