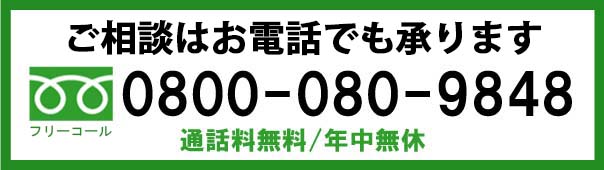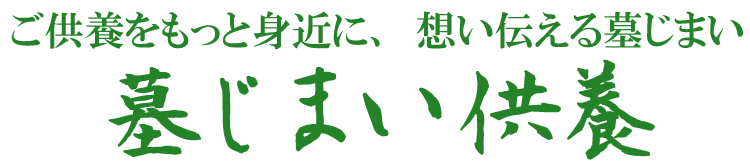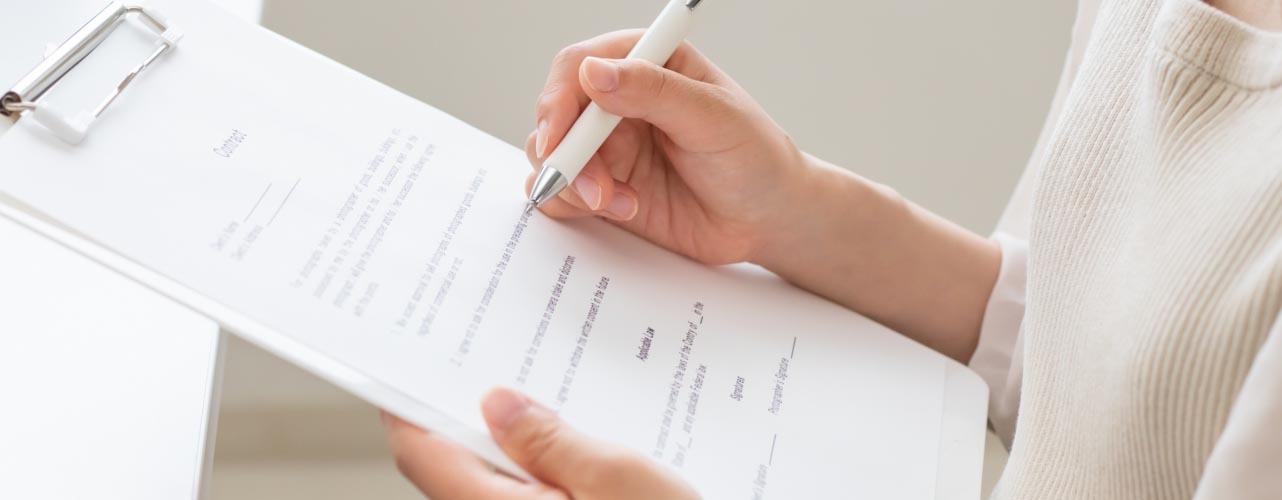みんなはどうして墓じまいをしたの?
お墓じまいをした理由や事情は皆それぞれございますが、最も多い理由を下記に並べてみました。
ご自身の事情とも照らし合わせてみてはいかがでしょうか。
何かのお役に立てるかもれません。
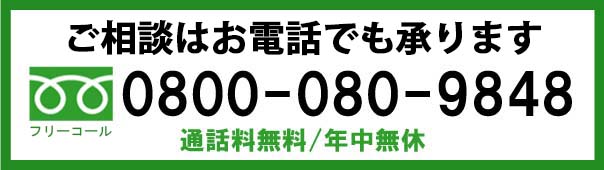
お墓が遠方でお墓参りが大変
若い頃は「里帰りついでにお墓参りに行こうよ」
「帰りに子供を連れて行楽にも行けるね」
と遠方に出かける理由も楽しく予定をたてられましたが、
「年と共に毎年の行事として田舎へお墓参りに出かけるのも体力的に厳しくなってきた」
「田舎にいた親戚も引越しやご不幸でもう誰も住んでいないので行く理由もない。」
とのご意見が多いです。
特に日帰りでは厳しい距離になりますと金銭的にも負担が生じますし「無理して日帰りして体調を崩した」とのご意見もチラホラと。
元々お墓は”親族や家族のお墓”であったのでしょうが、親族間でも生活環境が異なってくると事情も様々です。
もしあなたが、”家族がお参りしてくれるお墓”や”自分だけのお墓”の方がご自身のイメージに合っているのでしたら、自分たちが行きやすい場所で手を合わせられるようにしたいと考えるのが自然なことです。
長い目で見ると、負担になるお墓参り(ご供養)はお勧めできません。
跡継ぎ(墓守)がいない。
寺院によっては長男しかお墓を継ぐことができない等の規則がある場合もございます。
そうなると、”息子さんがいないご家族”や”長男さんにお墓を継ぐ意志がない”場合はお墓を継げないということになります。
お寺の規則としては長男がしっかりと墓守(お墓を継いで守る)する役割を大切にしていたと思いますが、現代ではお寺の規則も変更され、長男だけに継承権を限定することは減っているようです。
もし、檀家様同士の噂や人づての話を聞いただけの状態で不満を感じているようでしたら、一度お寺のご住職様にしっかりとご相談なさってはいかがでしょうか?
「以前は長男だけにお墓も継承を許可していたが、今は長男に限らず継げます。」と言った返答があるかもしれません。
もし、そこで話し合いがうまく進まない場合は、是非弊社にご相談を。相談は無料です!
お問合せ窓口 お電話は0800‐080‐9848
そもそもお墓に対する価値観が昔とは異なり、遠方にある田舎のお墓をそのまま管理するという考えが無く、また親御さんも”子供に負担になるお墓”や”お寺との付き合い”を今後どうすべきか迷っている方が多いように感じます。
とは言え、先祖のご遺骨をそのままにして良いわけではございませんので、やはり管理しやすい状態(場所)でご供養することが大切になると思います。
墓地を維持していく自信が無い。
お墓の維持にかかる費用は、
・寺院墓地の場合は主に年間管理料(年間護持会費)や寄付金などです。それとは別に法要をお願いする際には法要に対するお礼(付け届け)として別途数万円が必要であったり、通夜・葬儀・告別式、戒名(法名)授与などを菩提寺で行うことが決まりとなります。
・霊園や公営墓地の場合、基本的には年間管理料のみが維持費になります。
別途、法要を依頼する際には法要に対するお礼として数万円必要となります。
お客様からは「年金暮らしになるとたった数万円の管理料や付け届けが大きな負担となる」と言ったお話をよく耳にします。
”子供に負担になるお墓”というだけでなく、ご自身も”お墓参りが億劫”に感じられる状態であったり”お寺様との付き合い方”に悩んだり疑問を持ったりしている方も多いようです。
それぞれの立場やご事情がございますので一概には言い切れませんが、お墓(ご供養)に関わる皆がそれぞれのご事情を理解し合えるようにすることも大切と思わされることが多々ございます。
子供に迷惑を掛けたくない
今あるお墓を維持すること自体が、残された子供たちの負担になるのではないかというご意見・相談が非常に多いです。
負担の理由は、
- お寺との付き合いや寄付(経済的負担)
- お墓参りまでの距離・時間のリスク(経済的負担・時間的負担)
- お墓自体のメンテナンス維持費(経済的負担・管理負担)
- 将来の宗教選択の不自由(寺院墓地の場合、宗教的負担)
などがあげられます。
親族・家族間でも、長い時間をかけて考え方や方向性も変わります。
将来、選択を限定されないように、今のうちに整理しておきたい気持ちも理解できます。
将来に向けて前向きな選択をしたいものですね。
地震(自然災害)によりお墓が倒壊した
地震大国である日本において、地震被害によるお墓の破損や倒壊は起こりえます。
お墓のダメージにより、補修や補強を行うのか、建替えるべきかの選択を迫られますが、近年ではこの選択の一つに墓じまい(改葬)を行うという手段も加わっているようです。
そもそも、地震による被害が無くても、皆歳を重ねるにつれてお墓参りの度に草むしりからお墓掃除まで行うことがしんどくなり、またお墓が遠いこともあるでしょう。
それに加えて、今後お墓を守っている人がいるのかという継承者問題や、過疎化する土地にお墓がある場合は、墓地の管理者が不在のため墓地自体が荒れ果てているなどの状況を不安に感じているところに、地震等による被害を受けてお墓が倒壊したとなると、親族で話し合い、これを墓じまいの機会として身近な永代供養墓などに先祖の遺骨を改葬する事が増えております。
地震に限らず、台風などの豪雨による川の氾濫や土砂崩れ、地盤沈下などの自然災害も同じように墓じまいのきっかけになっているようです。
お寺との付き合いや寄付や付け届けが不安
こちらもよく相談される内容ですが、最近はコロナウイルスの影響で寺院行事も自粛され、寺院との付き合いや行事参加に対する相談は少なくなっている印象がございます。
対して、寄付や付け届けは世の中が不景気になればなるほど不満も増える傾向に感じます。
お寺と接触している檀家の高齢化もあり「年金暮らしになるとお寺への寄付、付け届けも厳しいからね。」というご意見も聞かれ、かといって年齢の若い方はお寺との付き合い自体に疑問を持つ事も多いようです。
いずれにしても、皆、供養をしたくない訳ではなく、お寺との関係に納得できる価値があるのかどうか?で判断している方が増えた様に感じます。これは、以前に比べてお寺様と檀家様の関係が変化したことも影響しているのかもしれません。
参考記事:墓じまいにかかる費用
近くの樹木葬に移したい
「遠いお墓を墓じまいして近くの樹木葬にお骨を移したい」とのご要望は多くございますが、よくお客様がイメージなされている”木の下で土に還れる樹木葬”と実際に販売されている”樹木葬”には大きな違いがございます。
実際に販売されている樹木葬は、お寺の境内などで空いた区画等に樹木葬が設けられておりますが、そのほとんどが土に還るというよりも、期限を何年か決めてその期間は一旦そちらに埋蔵されるスタイルの樹木葬となっております。
そして期限が過ぎると同じ境内の合祀墓に移されるケースが多いです。
本当の意味で”お骨が土に還る自然派樹木葬”は数が少ないですが、自宅からの利便性や価格比較などで判断なされ、土に還る樹木葬のイメージとは違っても、近くて行きやすい”土に還れない樹木葬”や”永代供養墓”を契約なされる方が多いです。
樹木葬に対する先行イメージとはことなっても、将来の事を考えて利便性を優先させる現実的な考えのお客様が増えましたね。
自然散骨や合祀墓にしたい
最近は”自然に還る自然散骨”や”他の他人の方ともお骨が混ざる合祀墓”に抵抗なく、自ら希望なされる方も大変増えております。
特に合祀墓は、埋葬された後のご遺骨が他人と一緒に混ざってしまうのですが、最近では「合祀墓でよいです。」と仰るかたのとても増えました。
また、自然散骨には海洋散骨と山散骨などの”お骨を自然に還す”イメージが強いと思いますが、実際に販売されている自然葬は海洋散骨タイプが多いです。
価格の面ではご家族貸し切りの船舶チャーターだと約20万円前後かかり、お客様にも「意外と高いね」と言われることも多いですが、海洋散骨は天候などで出航できないこともあり、一般の陸地供養施設に埋葬するよりも大掛かりな行事になることが多いので仕方のないことですね。
しかし、海洋散骨にも散骨方法は大きく分けて3つございまして、
- 貸し切りチャーター散骨:船を貸し切り状態で散骨する。価格は20万円前後
- 合同散骨:ほかの方と一緒に乗船して散骨する。価格は15万円前後
- 代行お任せ散骨:お客様は乗船せずに業者に散骨を代行してもらう。価格は5万円前後
などを選択できます。
都立霊園の施設変更制度を利用したい
都立霊園施設変更制度とは、都立霊園にお墓を持っている方で、将来墓守(後継ぎ)がいないため無縁墓になる等の理由でお墓が維持できなくなる方を対象に、お墓(墓所)を東京都に返還し、都立霊園内に建築された、従来のお墓ではない”永代供養墓”であるの合葬埋葬施設にご遺骨を埋蔵できる制度です。
この制度のメリットは、通常、墓じまいをすると、新たにご遺骨を納めるための供養施設を探す事が必要となり、その供養施設の使用権利を購入する為お金もかかりますが、施設変更制度を使うと都立霊園敷地内で合葬埋葬施設へのご遺骨の移動ができて、あとは墓じまい工事にかかる費用のみとなりますので、全体的にリーズナブルにまとめることができます。
また、実際にお墓がある都立霊園から施設変更制度の資料を取り寄せた後、必要書類を墓じまい業者に渡せば墓じまい代行していただけます
現在、都立霊園は合わせて8霊園有り、都立霊園全体の利用者は約29万人です。
ご自身のお墓が将来無縁になる可能性が高く、自分が最後の墓守となるであろう方々からすると、先祖供養に対して感じていた不安を払拭してくれそうな制度といえそうです。
参考外部サイト:都立霊園 施設変更制度